 現場監督
現場監督コンクリートの養生って、期間は何日必要?
湿潤養生が必要な日数と、型枠を外してもいいコンクリート強度について知りたいな。
こんな疑問に答えます。
 ランメイシ
ランメイシ公共の土木工事では、コンクリートの養生期間がとても重要ですね。
コンクリート標準示方書(施工編)は土木学会が5年ごとに発行する、以下の緑色カバーが目印の書籍です。値段も高くて個人で買うには財布に優しくありません…。
 ランメイシ
ランメイシ公共工事では現場に1冊、最低でも会社に1冊は必要です。
この記事ではコンクリートの養生について、公共の土木工事で求められる施工管理の方法を徹底解説します。
【超重要】コンクリート湿潤養生期間の目安
コンクリート標準示方書施工編(2023年制定)によれば、コンクリート湿潤養生のポイントは以下2点です。
- 打込み後のコンクリートは、その部位に応じた養生方法により一定期間湿潤状態に保つ。
- 湿潤養生の期間は、使用するセメントの種類や養生期間中の環境温度等に応じて、施工実績、信頼できるデータ、あるいは試験等により定めるものとする。
 現場監督
現場監督湿潤養生が必要なのはわかるけど、湿潤養生の期間で「施工実績」とか「信頼できるデータ」が無いはどうするの?
 ランメイシ
ランメイシコンクリート標準示方書に記載の「湿潤養生期間の目安」を参考にすると良いですよ。
コンクリート標準示方書に記載の「湿潤養生期間の目安」は以下の通りです。
| 日平均気温 | 早強ポルトランドセメント(H) | 普通ポルトランドセメント(N) | 混合セメントB種(BB) | 中庸熱ポルトランドセメント(M) | 低熱ポルトランドセメント(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15℃以上 | 3日 | 5日 | 7日 | 8日 | 10日 |
| 10℃以上 | 4日 | 7日 | 9日 | 9日 | ※ |
| 5℃以上 | 5日 | 9日 | 12日 | 12日 | ※ |
※ 15℃より低い場合での使用は、試験により定める。
 ランメイシ
ランメイシ公共の土木工事では、基本的に普通ポルトランドセメント(N)か高炉セメントB種(BB)を使うので、この2つだけでも覚えておきたいです。
施工プロセスチェックや書類検査のときに、「現場で本当にこの日数で湿潤養生していたか、証明できる?」とちょっとイジワルなことを聞く発注者がいます(笑)
湿潤養生日数を証明する方法を2つ紹介します。
- 打設箇所・生コンクリート打設日・湿潤養生完了日を書いたコンクリート湿潤養生管理表を書類としてまとめておく。
- 生コンクリート打設日、湿潤養生1日目~7日目など、必要な日数の湿潤養生状況写真を撮っておく。
 ランメイシ
ランメイシここまでやっても、「毎回打設分の写真は無いの?」とか言われたら、写真管理基準に書いてないですからって答えましょう(笑)
温度変化と乾燥への対応が決め手
コンクリートは、打設後も時間とともに品質が変わります。
適切に養生できるかどうかが、強度や耐久性を確保するうえで重要です。
養生のポイントや強度を予測する方法なども交え、施工段階で把握すべきコンクリートの強度特性や注意点について考えてみましょう。
コンクリート構造物の安全性や耐久性を確保するには、水セメント比や設計基準強度を適切に設定する必要がありますが、初期養生がそれらの性能を大きく左右することに注意しなければなりません。
コンクリート打設後の脱型に関連して、土木学会のコンクリート標準示方書では、強度の規格値として以下の2点を示しています。
1つ目は、型枠や支保工の取り外しに必要なコンクリートの圧縮強度です。
施工時の安全性のほか、構造物の品質や性能を確保する目的で、下の表のように規定しています。
| 部材面の種類 | 例 | コンクリートの 圧縮強度 |
|---|---|---|
| 厚い部材の鉛直または鉛直に近い面 傾いた上面 小さいアーチの外面 | フーチングの側面 | 3.5N/mm2 |
| 薄い部材の鉛直または鉛直に近い面 45度より急な傾きの下面 小さいアーチの内面 | 柱 壁 はりの側面 | 5.0N/mm2 |
| 橋・建物等のスラブおよびはり 45度より緩い傾きスラブ はりの底面 | スラブ はりの底面 アーチの内面 | 14.0N/mm2 |
例えば、コンクリートを型に流し込んだ後、側面に取り付けた型(型枠)を外すときは、コンクリートが重さや上に積まれる荷物に耐える強さを持つようになるまで、しっかりと時間をかけて成長させます。
施工現場では、これを「養生」と呼んでいます。
つまり、コンクリートがしっかりと固まり、自分の力で立てるようになるまで、時間をかけて大切に育てるんですね。
部材底面の型枠の場合は、上載荷重や自重による曲げ作用に対して抵抗し、部材に不具合が生じないレベルの強度が発現するまで養生する必要があります。
コンクリートが型枠に収まっている間は養生中とみなされます。
2つ目は、激しい気象作用を受けるコンクリートの養生終了時の所要圧縮強度です。
寒中コンクリートの初期凍害を防ぐために、養生温度を5℃以上に保つことを前提とし、養生終了時の圧縮強度を、断面寸法と構造物の露出状態で以下の表の通り規定しています。
| 構造物の露出状態 | 断面が薄い場合 | 断面が普通の場合 | 断面が厚い場合 |
|---|---|---|---|
| しばしば凍結融解を受ける場合 (次の春までの凍結融解が数10回程度) | 15N/mm2 | 12N/mm2 | 10N/mm2 |
| まれに凍結融解を受ける場合 (次の春までの凍結融解が数回程度) | 5N/mm2 | 5N/mm2 | 5N/mm2 |
また、コンクリートの温度が急激に低下しないように所要の圧縮強度が発現した後も、2日間は0℃以上に保たなければなりません。
養生日数で管理する
養生の終了時期を強度で決めるのは理にかなった方法ですが、実際には工事の途中で強度を見ながら養生を終えるのは少し複雑です。
だからこそ、強度の出方と養生日数の関係を知っておき、必要な強度に達するまでの日数だけ養生する方法が選ばれています。
セメントが水と反応すると、養生温度を上げると反応が速まり、早く強度が出るんですね。
 ランメイシ
ランメイシ逆に、養生温度が低いと、強度の発現が遅くなります。
表の下に書かれているのは、通常のコンクリートの断面の大きさで考えた場合、初期凍害を防ぐために必要な養生日数の目安です。
これは、セメントの種類と養生温度の組み合わせによって示されています。
| 5℃以上の温度制御養生を行った後の 次の春までに想定される凍結融解の頻度 | 養生温度 | 早強ポルトランドセメント(H) | 普通ポルトランドセメント(N) | 高炉セメントB種(BB) |
|---|---|---|---|---|
| しばしば凍結融解を受ける場合 (次の春までの凍結融解が数10回程度) | 5℃ | 5日 | 9日 | 12日 |
| 10℃ | 4日 | 7日 | 9日 | |
| まれに凍結融解を受ける場合 (次の春までの凍結融解が数回程度) | 5℃ | 3日 | 4日 | 5日 |
| 10℃ | 2日 | 3日 | 4日 |
同じセメントについて見てみると、養生温度が高くなれば養生日数が少なくなります。
また、セメントごとに反応性が違うので、同じ養生温度でも必要な養生日数はそれぞれのセメントで異なります。
冬場の給熱養生は乾燥に注意
冬季は温度が低いので水和反応が阻害され、強度の発現が遅れます。
さらに外気温が-5℃程度以下になると、初期凍害を受けて所要の性能が得られない恐れがあります。
このような場合は、水和反応が円滑に進むように保温や給熱による養生を行う必要があります。
給熱養生にはジェットヒーターや蒸気のほか、面積が小さければ投光器や練炭を使うこともあります。
ジェットヒーターは一般的に使われていますが、使用する際は乾燥に注意しなければなりません。
温度を高める効果が大きい半面、熱風を供給することによって乾燥させてしまう恐れがあるからです。
 ランメイシ
ランメイシ構造物の表面が乾燥してしまうと、ひび割れが発生するリスクがあります。
床などに散水して、十分な湿潤状態の下で給熱することが重要です。
温度の急変を避ける
保温・給熱養生を行う際には、養生後の温度の下げ方にも注意が必要です。
せっかくきちんと養生して強度が出ても、急に外気にさらせば、ひび割れが発生してしまいます。
トンネル工事やダム監査廊の工事で、仕切り扉を設置して養生しておきながら、所定の日数がたって取り外したときに、外気によってひび割れが入ったという失敗例は多いです。
温度の急変は絶対に避けなければなりません。
供試体と構造体の強度は異なる
供試体の強度は実際の構造物の強度を適切に表しているとは言えません。
土木分野では構造物の規模が比較的大きく、表層部の近傍を除いて大部分のコンクリートが実質的に湿潤状態にあります。
さらに、供用開始までに日数がたって強度の増進が見込まれます。
水中養生の材齢28日における供試体の強度は、封かん養生の材齢91日における供試体の強度に匹敵します。
土木構造物のように部材断面が大きく、外部からの養生が部材の内部まで及ばない条件では、封かん養生と同等の養生がなされていると考えられます。
つまり、標準養生の材齢28日強度は、型枠内に打設したコンクリートの材齢91日以降の強度を代表するものと判断できるでしょう。
まとめ
コンクリートの品質や強度を確保する上で欠かせないのが、適切な養生です。
施工後のコンクリートは時間とともに品質が変わりますが、適切な養生ができるかどうかが強度や耐久性の確保に直結します。
特に冬季では水和反応が阻害され、初期凍害のリスクも懸念されます。
このため、保温・給熱養生が必要とされます。
しかし、養生後の温度の急激な変化はひび割れを引き起こす可能性があり、慎重な管理が求められます。
コンクリートの強度は初期の供試体の強度だけでなく、構造物全体の性能も考慮する必要があります。
供試体の強度は実際の構造物を十分に代表しているわけではないため、構造物の規模や湿潤状態などを考慮して総合的な判断が必要です。
養生期間や温度管理においては、コンクリートの用途や条件に応じて適切な対策を講じることが重要です。
水中養生や封かん養生など、状況に応じた適切な養生方法を選択し、品質を確保する努力が求められます。
最終的には、コンクリートの品質管理においては供試体の強度だけでなく、構造物の実際の性能や条件を踏まえた総合的なアプローチが不可欠です。
プロの視点でコンクリートの施工に臨み、適切な管理と養生を行うことが、安全で耐久性のある構造物を実現する鍵となります。
品質の高いコンクリート施工の方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
Q&A
- 養生の重要性はどのようにコンクリートの品質や耐久性に影響するのでしょうか?
-
養生は施工後のコンクリートの水和反応を管理し、強度や耐久性に大きな影響を与えます。適切な養生ができるかどうかが、コンクリートの品質を確保する上で不可欠です。
- 冬季のコンクリート施工において、保温・給熱養生はなぜ必要なのですか?
-
冬季は温度が低いため水和反応が阻害され、初期凍害のリスクが生じます。保温・給熱養生は水和反応を促進し、適切な強度を確保するために不可欠です。
- 供試体の強度と実際の構造物の強度にはどのような関係がありますか?
-
供試体の強度は実際の構造物を十分に代表しているわけではありません。構造物の規模や湿潤状態などを考慮して、総合的な判断が必要です。
- 養生後の温度変化がひび割れを引き起こす可能性があるとされていますが、なぜですか?
-
養生後の温度変化がひび割れを引き起こす可能性があるとされていますが、なぜですか?
- コンクリートの養生期間や温度管理において、具体的な適切な対策はどのように選択されるべきですか?
-
養生期間や温度管理は用途や条件により異なります。水中養生や封かん養生など、状況に応じた適切な対策を選択し、品質を確保するための最善の努力が求められます。
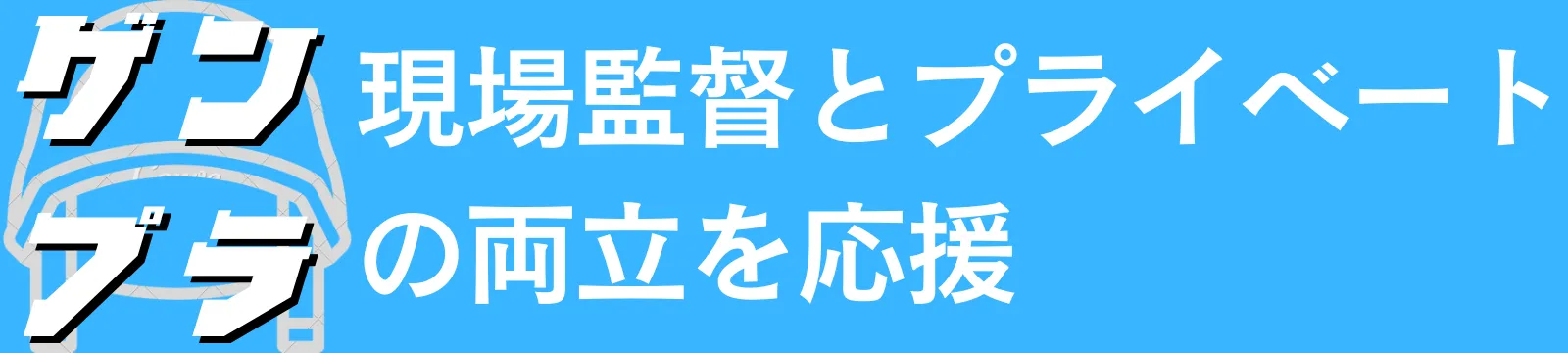


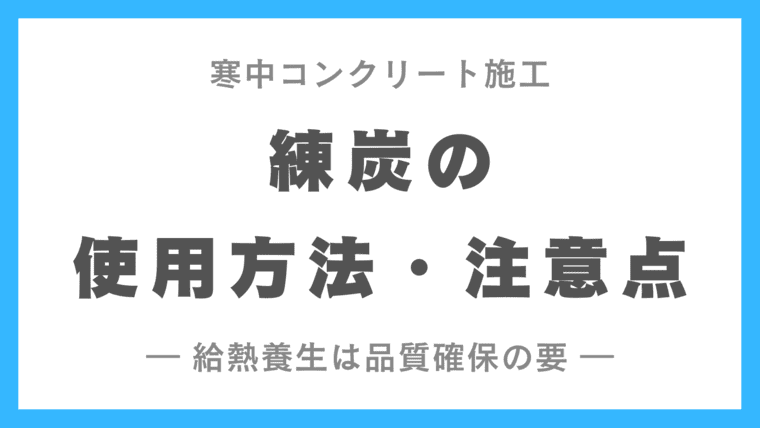
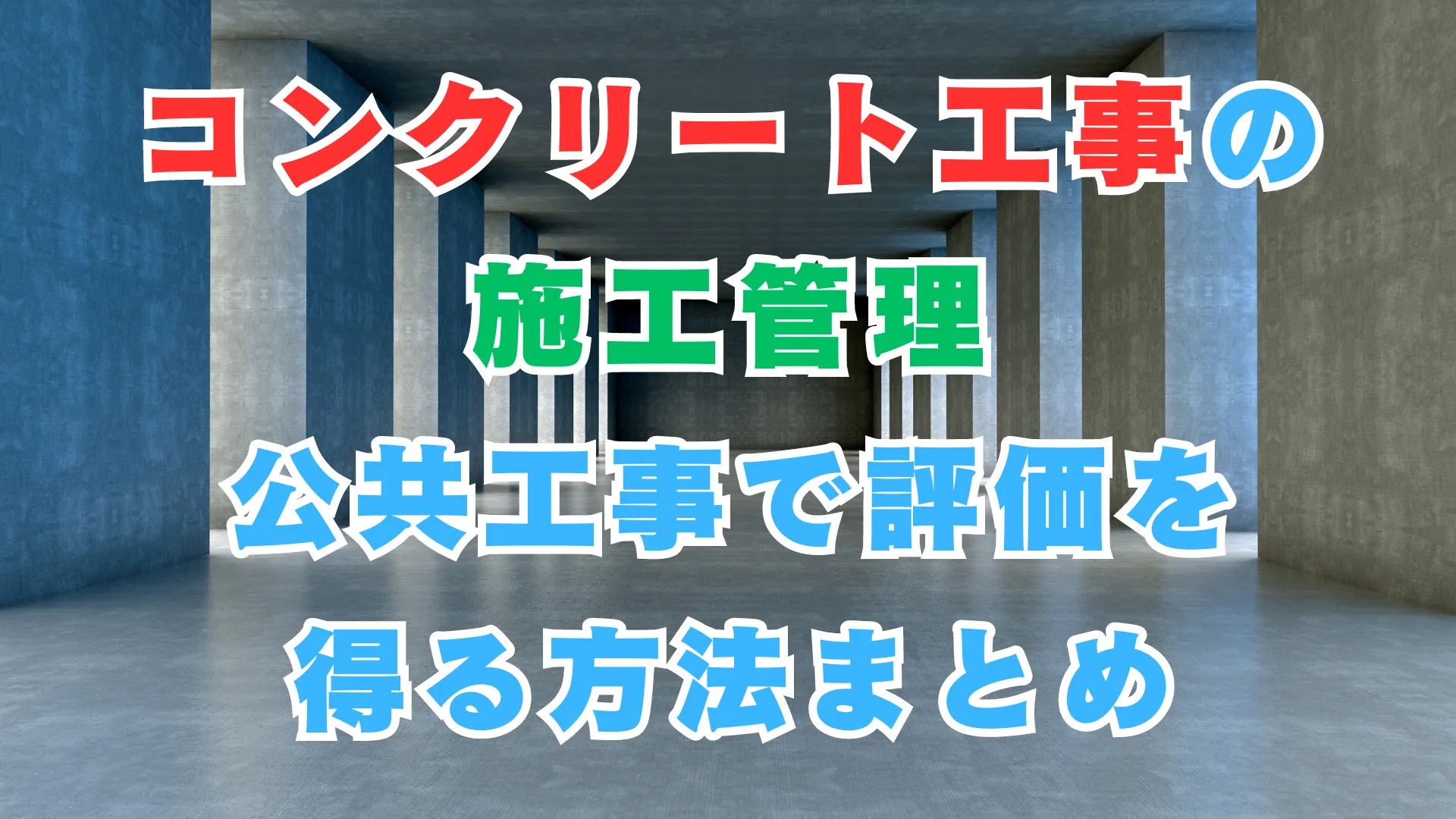
コメント