現場監督が持つべき8つのスキルと高め方を施工管理16年以上のプロが解説
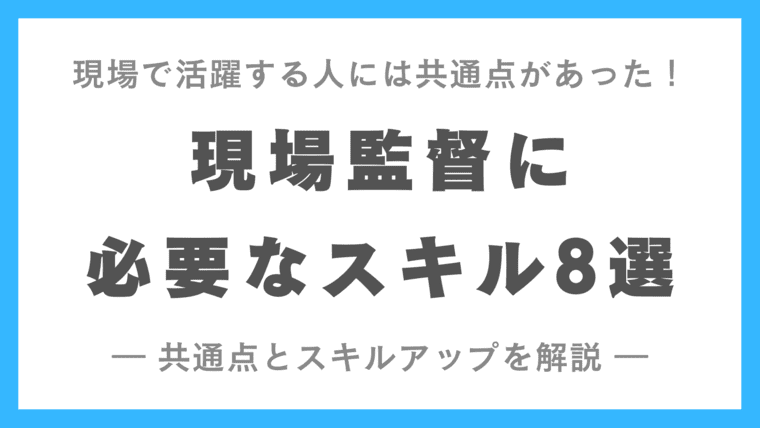
建設現場の現場監督をやっていると経験する、トラブルが発生して解決法が見つからない技術的な問題や、人間関係のトラブルによる問題。
こういった想定外の問題で路頭に迷ってしまうといった経験はありませんか?
『頑張るぞ!』と意気込んで始めた現場監督。
いざ現場に出ると自分の思い通りに仕事が進まなかったり、トラブルによって仕事のルーティーンがめちゃくちゃ。
さらには、上司から怒鳴られたりしてメンタルを病んでしまい、うつ病やノイローゼになってしまうケースも。
結果、現場では信頼関係を築くことができず、現場監督という立場なのにリーダーシップは全く取れない。
でも、こんな問題は8つのスキルを身につけることで解決することができるんです。
本記事では、施工管理を行う現場監督に必要な以下8つのスキルについて解説します。
- 自分の思い通りに現場を管理するスキル
- 現場の問題点を予測するスキル
- 問題解決の順序を決めるスキル
- 現場にトラブルが発生した時のメンタルスキル
- 現場でリーダーシップをとるスキル
- 相手を引き込む会話スキル
- 工事関係者の信頼を得るスキル
- 事故を予防するスキル
ちなみに、上記のスキル以外に原価管理のスキルも大事です。
しかし、施工管理技術者ならまずは『現場力』が1番大事なので、本記事では現場力について解説します。

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ
現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!
保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士
主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ
現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!
保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士
主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事
スキル1:自分の思い通りに現場を管理するスキル
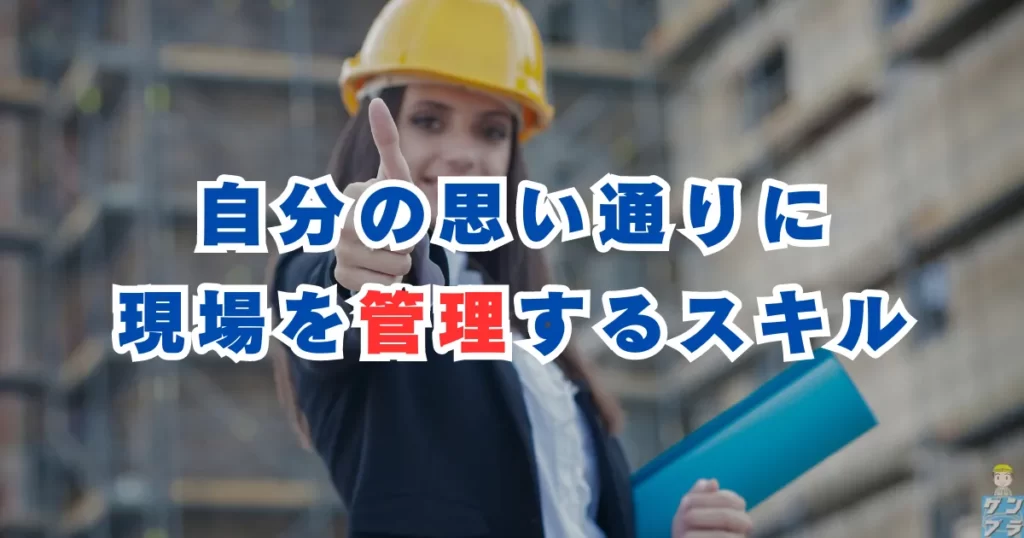
現場監督に必要なスキル、1つ目です。
自分の思い通りに管理するスキルの考え方と、現場での運営のコツについて。
現場を1つの会社と考えてください。
会社では年間の目標や行動指針を計画し、実行していますが、現場でもやります。
自分の思い通りに現場を管理するスキルについて、以下の記事でより詳しく解説しているので、参考にしてくださいね。
現場で「目標」を掲げる
現場を会社として考えるという点について、
「現場は現場。会社に縛られることなくやりたいんだよ」
と思う方もいると思います。
でもまず、現場を特別扱いせずに1つの会社として考えてみてください。
現場を会社と同じように目標を掲げます。
そうすると、自分が目指す方向が明確になります。
この目標の内容については、次の記事で具体的に解説しています。
「現場ルール」を定める
次に現場内でのルールについてです。
この現場に来たら、
これだけは必ず実践してくださいという、現場ルールを設けるということです。
どんな現場ルールを定めると良いのかについては、次の記事で具体的に解説しています。
「現場ルール」は、次の場面で必ず宣言するようにします。
- 現場入場前の事前連絡
- 現場入場時の新規入場者教育
- 朝礼・KYミーティング
- 安全教育
- 安全協議会
宣言する頻度はしつこいくらいが良いです。
なぜなら、毎日聞かされると嫌でもが頭に残るからです。
 ランメイシ
ランメイシ話を聞き流していたり、ぼーっとしていて聞いていない人、結構いますからね。
僕たちはスマホやパソコンを使い、ネットから毎日多くの情報を得ていますよね。
1日30分で20個の情報を見ているとすれば、1週間で140個もの情報に接触していることになります。
しかし、そのうち記憶に残っているのは、たったの4個。
情報吸収率はわずか3%です。
休憩時間になればすぐにスマホを見て、
自分の知りたい情報をチェックするという人も多いでしょう。
しかし、たったの1週間でその97%を忘れてしまうんです。
なので、現場ルールも現場では毎日宣言しないと、なかなか浸透しません。
「目標」と「「現場ルール」を必ず口に出すことで、自分自身のメンタルを鍛えられる
仕事も人生も「ABC」が大事、という言葉があります。
ここの「ABC」とは、
「あたりまえのことをバカになるほどちゃんとやる」
ということで一見おかしな言葉にも見えるかもしれませんが、素晴らしい教育効果を得ることができます。
自分自身もブレないために、「目標」と「現場ルール」を必ず口に出すことで、自分自身のメンタルを鍛えることができます。
なぜこれでメンタルが鍛えられるのかというと、自分で決めたことだから必ず実践すると心に刻んだ時にメンタル面の基礎ができあがります。
押しつぶされそうな不安や、さまざまなプレッシャーに勝つためには、
自分で決めたことを徹底的に実行することです。
これを毎日繰り返していくと、より強靭なメンタルを形成することができます。
『凡事徹底』が自分自身のメンタルを強くする
凡事徹底するということが、どれほど自分自身のメンタルを強くするか、実践してみてください。
「現場ルール」の定め方については、こちらの記事で具体的に解説していますが、
どんなシンプルなことでも大丈夫です。
例えば、会う人に必ず「あいさつをする」でもOKです。
毎朝、現場の安全巡視の時、打合せの時など。
あいさつを励行していると現場が1週間で変化します。
現場で働く人全員があいさつをするようになります。
「現場ルール」は「あいさつをする」
お金がかからない、手間がかからない、シンプルですが、素晴らしい現場ルールだと思いませんか?
いきなり難しい「現場ルール」を設けてもいいのですが、まずは「あいさつをする」といった簡単なことから初めて、次の工事ではステップアップして、こうしよう。
といった感じで行うのが良いですね。
現場運営の4つのコツ
現場運営の4つのコツは、次の通りです。
- 成功体験教育
- 目標となる人
- 謙虚さ
- 感謝の心
成功体験教育
この手順で工事を進めたら、作業がスムーズにでき、安全を確保しながら無事故で完了した。
というような成功体験を言います。
これを作業手順として記録に残し、伝えていくことが必要になります。
これが経験値となり、将来に生きてきます。
同じ工事でなくても、手順が似たような作業の時に
「あの時に成功した作業手順でやればいけそうだ」
という記憶の引き出しになります。
目標となる人
現場で働いている人の中には、目標となる人が必ずいると思います。
職長さんが素晴らしければ安全な作業を心がけてくれます。
働いている人の中にも、質問をするとしっかりと答えが返ってきて、
作業手順の提案をしてもらえることがあります。
専門職として長年働いていることで、素晴らしい経験をたくさん持っている人たちです。
そのような優秀な人たちを安全大会で表彰すると、現場の士気はあがります。
現場内の人以外でも、他には土砂運搬などを行うダンプトラック運転手。
運転手の方には、巡視の際に運行状況も管理し、
丁寧かつ慎重な運転をしてくれている運転手にも表彰することで、
運転手全員がより安全な運行を意識してくれるでしょう。
こうすることで、
「この現場の監督は自分たちのことを認めてくれている」
と思ってもらえれば、現場はより良い回転をしていくことになります。
謙虚さ
現場監督が指示を出す際、高飛車・高圧的に話すのか、
申し訳ないけれどと言って、下から持ち上げるように話すのかでは、
のちの作業に大きな違いが出てきます。
誰でも、立場が逆になってみればわかることですが、
「おい、これをやっておけ」
と言われて、気持ちよくやってもらえるわけないですよね。
現場監督には、協力会社の職人さんらが気持ちよく作業できるよう、現場の雰囲気づくりが大切です。
作業の依頼をしたいときでも、無駄話を1~2分してから、
「申し訳ないけど、このように変更してもらうと安全で事故防止につながると思うので、お願します」
と言われたら、やらなくてはいけないかなと思ってもらえると思います。
そして、あなた自身の仕事、施工管理です。
管理をするにはまず、現場で働いている1人1人が同じ方向を向いて安全に作業を進めてもらえるようにする必要があります。
そして、働いている1人1人にその気になって作業をしてもらい、高品質な製品を造り上げることです。
土木施工管理技士の資格を取得したり、技士補の称号を持っていたとしても、現場を思い通りに動かすポイントはその資格範囲には無いので、スキルとして身に付けるしかありません。
感謝の心
現場に限らず、いつも持っていたい心です。
工事を請け負っているのは、元請会社です。
元請会社には、技術力があり、品質を確保するノウハウがあり、
図面を見る能力があるので、自ら工事を遂行できれば理想的です。
ですが、現実には無理があるというか、ほぼ不可能ですよね。
そのため、重機、クレーン、鉄筋工、型枠大工など
様々な職種の機械と職人さんを抱えていなければいけません。
コンスタントに仕事を受注できるという確約があれば、
この大世帯を維持することも可能です。
でもそれが無理な話なのはある程度、
現場監督を経験している方ならばわかるのではないでしょうか。
なので、現場監督が工事を遂行するためには、
自分の代わりに働いていただく各工種の専門業者さんと一緒に仕事をすることになります。
だから、自分の代わりに働いていただいているという気持ちを持たないと、
現場で働いている人々に感謝の気持ちが伝わりません。
感謝の気持ちを持って現場を見渡せば、コミュニケーションを構築できるし、
働いている人々全員が、良いものを造ろうという気持ちになると思います。
「お前のところに発注したんだから、お前がしっかりやればいいんだ」
という意見では、利益が上がらないばかりか、事故が発生する可能性もあります。
感謝の気持ちは、現場のコミュニケーションを良くするための心のお守りと考えると良いですよ。
スキル2:現場の問題点を予測するスキル
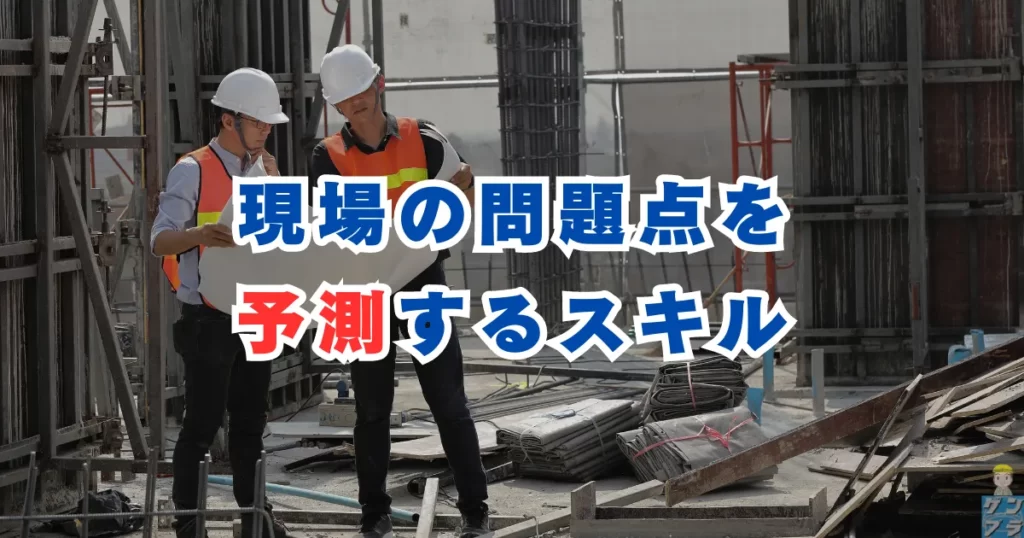
現場の問題点を予測するスキルについて。
得た情報をどう扱うかがポイントです。
立場上、現場で1番情報を持っている。
というより、1番情報を持っていなければいけないのは、現場監督です。
- 発注者や関係機関との打合せ内容、
- 協力業者との契約内容、
- 工事に使用する材料の価格、
- 実行予算
- 工事の進捗率・出来高
- 社内の情報
これらの情報は、現場監督に集中しているわけです。
施工管理の経験年数が1~3年目くらいだと、
経験が浅い現場監督さんは予算や出来高など、
特に原価管理についてはあまり関与しないかもしれません。
ですが、いずれ現場代理人や監理技術者の立場になれば原価管理は必ず行う業務です。
あまり理解できなかったとしても、
何にどれだけのお金がかかっているのかは上司に聞いておくと、今後の参考になります。
現場監督は、得た情報を現場の関係者に全て伝えられているかがポイントになります。
発注者との打合せの内容は、その度に情報が更新していきます。
その更新した情報も、現場監督は現場の関係者に全て伝えなければいけません。
やってしまいがちな間違いとして、
- 自分だけが知っておけばいいだろう。と思って伝えないパターン
- 言わなくても、それくらいわかっているだろう。と思って伝えないパターン
こういった間違った考えは情報が現場に届かず、次のようなリスクが出ます。
- 事故発生リスクの引き上げ
- 品質の低下
- 発注者・協力会社への信頼度の低下
現場は様々な業者が協力し合って出来上がります。
全ての作業を自分自身で行うことができれば問題ありませんが、
体がいくつあっても足りなくなるのは目に見えますよね。
したがって、毎日変化していく現場の情報は
現場の全ての人に伝える必要があります。
建設現場はチーム戦であり、個人戦ではありません。
情報は現場の人全員に行きわたっていないと、全員が同じ方向へ進むことができません。
もし、誰かが間違った方向へ向かっていると、トラブル発生の原因になります。
現場で働く人は20代~60代と幅広く、考え方や技術レベルも異なります。
同じ話でも違った解釈をされたまま進んでいくことがあります。
対策をしようにも、忙しいときに個別で説明をしている時間を確保するのは難しいですよね。
なので、例えば朝礼前や休憩時間などに、仕事に関する話以外に世間話など、
仕事とは全く関係無い話をして、相手の人柄を把握するのも現場監督の役目です。
次の記事で、現場の問題点を予測するスキルについて、さらに詳しく解説していますので、よければ参考にしてみてください。
スキル3:問題解決の順序を決めるスキル

問題解決の順序を決めるスキルについて。
簡単な問題から解決していくことがポイントです。
山登りを始めた人が、いきなりエベレストに挑戦する人はいないし、無茶であることは明らかですよね。
まずは小さくて登山道も整備された山から始めて、徐々に高い山に挑戦しますよね。
問題解決の順序も同じです。
現場で発生する「問題」=「ストレス」多いが、「ストレス」は必要なもの
現場で発生する問題は5つ、6つ、7つと、場合によっては追い打ちをかけるように次々と起きますよね。
問題が重なって、どれから手を付けたらいいのかわからない。
となってしまった経験も多くいと思います。
こんな状況が多いからこそ、若手の現場監督さんは
「もう無理だ…こんな仕事嫌だ…」
という気持ちになることがあります。
そうなってしまう前に問題を解決しておく必要があります。
あなた自身の心にプレッシャーとして重たくのしかかり、ノイローゼになりそうな悩みをそのままにしていると、本当に病気になりかねません。
「悩み」=「ストレス」となり、悩みの数に比例してストレスも増大して仕事が嫌になると思います。
でも、ストレスは0にしてしまってはダメなものなんです。
なぜかというと、ストレスの原因となる「悩み」・「プレッシャー」・「苦労」を無くしてしまうと、問題を乗り越えた先の「達成感」や「成長」も無くなってしまうからです。
問題や悩みを乗り越える方法
悩んでいることを紙か、スマホのメモ帳などに書き出してみてください。
とにかく、頭の中で考えている状態から一旦、書き出して悩みを「見える化」します。
ちなみに悩みの書き方で大事なことは、誰かに悩みを相談するように悩みを書くということです。
例えば、
「上司の〇〇に怒られてムカつく」
という書き方ではなく、
「上司の〇〇に説明が下手で何が言いたいのかわからんって、いつも怒られるんだけど、どうすればいいかな?」
という書き方にしてください。
書き出したら、今度はその解決法をググるなど、インターネットで検索します。
例えば、
「説明 下手 解決」
「説明 上手に」
検索の結果、結論から話して、その後に理由、という順序で話すといった解決法が出てくると思います。
そして、その解決法(結論から話す)を実践します。
悩みを抱えたまま放置しないことが大切です。
問題は難しいものより簡単なものから解決していく
現場に複数の問題がある時に、解決する順番はどうするのか。
簡単ですぐに解決できるものから順に手を付けていきます。
RPGゲームなどで、ゲームが始まっていきなりラスボスと戦うことは普通、無いですよね。
弱い雑魚敵と戦ってレベルを上げながら進んでいく。
これは仕事においても同じで、すぐに片付きそうな仕事から手を付けるのがポイントです。
意外と、簡単な問題を1つ解決したら、もう1つ解決できたということもあります。
それに、簡単な問題から順番にやることで、大きな問題と思っていたことが中程度の問題に変化することもあります。
簡単にできることから行うと優先順位をつけることで、時間がかからずに早く解決できることから、あなた自身の心の安定につながります。
次の記事で、問題解決の順序を決めるスキルについて、さらに詳しく解説していますので、よければ参考にしてみてください。
スキル4:現場にトラブルが発生した時のメンタルスキル

現場にトラブルが発生した時のメンタルスキルについて。
現場監督という仕事をするうえでメンタルの成長と安定は重要です。
社会人最初のキャリアが現場監督という方は、現場監督だけがトラブルが多いと思い込んでいる方が多いです。
なので、嫌になったら他の職種にしようと考えると思います。
ですが、トラブルの無い仕事はありません。
どんな業種でも、どんな仕事でもトラブルは発生します。
現場監督をやっていてトラブルが嫌だから異業種へ行ったとしても、また嫌になって異業種へ…の繰り返しになる末路です。
どんな業種でも、どんな仕事でも、トラブルを解決することが本当の仕事です。
トラブルを解決してきた人が、必要とされる人になっていきます。
トラブルをチャンスと捉える
トラブルは避けようとするほど、何故か近づいてきます。
特に繁忙期など、トラブルだけは起きないでくれと思った時に限って、トラブルが起きるんですよね。
トラブルは不確定要素なので起きた時は、想定外だったと考えがちです。
でも実は、忙しくてトラブルになりそうな兆候を見逃していただけというケースもあります。
そこで、考え方を変えて現場にのぞんでみます。
「自分の現場だけは、トラブルは起きないでくれ」
と考えるのではなく、
「自分の現場だからこそ、トラブルは必ず起きる」
と考えてください。
多くのトラブルを経験し、原因の追及・解決方法を確定できれば、次からはそのトラブル発生の予防ができるし、別のトラブルにも同様の方法で解決できるかもしれません。
トラブル発生といった「失敗」は絶対にしたくないと思うでしょうが、トラブルから逃げ続けていると、いつかしわ寄せがきます。
トラブルは起きるものと、心の準備をしておけば、いざトラブルが起きても平常心でいられるはずです。
苦労したくないから、トラブルは絶対に起きてほしくないと思いたいところですが、前述したように、トラブルの無い仕事はありません。
トラブルが起きない仕事は無いから、トラブルを楽しもうと考えるのがポイントです。
メンタルスキルについては次の記事でより詳しく解説していますので、よければ参考にしてみてください。
スキル5:現場でリーダーシップをとるスキル

現場でリーダーシップをとるスキルは、あなたが現場代理人や監理技術者という立場になる時、必要なスキルです。
リーダーシップって、自分が率先して皆を引っ張っていくものと思うかもしれませんが、だからといって周囲の意見を捻じ曲げていると、良い現場にはなりません。
例えば協力会社の作業員や会社の後輩に対して、良い点を褒めてあげたり、話をしっかり聞く。
こういったことができていれば、80%はリーダーとして優秀と考えて大丈夫です。
褒めてあげることで、現場が明るくなりますし、良い人間関係を築くきっかけになります。
逆に怒ってばかりいると、現場は暗くなるし、会話をしたいとも思わなくなってしまいます。
重要なことも意思疎通ができなくなり、事故の原因になりかねません。
気を付けたいのは、あなたが現場代理人の立場で現場を任された時。
自分は偉いと思うようになり、後輩の意見や評価など気にもしなくなってしまうことがあります。
例えば、ギャンブルに大勝ちしてお金に余裕ができたから余計なものを買ってしまうとか、無名だったユーチューバーがバズって突然有名人になり、天狗になっている状態。
あなた自身も上司がムカつく、と思った経験はありませんか?
あなた自身が後輩を持つようになると、同じように後輩に値踏みされていることを自覚しながら接しないといけません。
上司の悪いところを見つけるのは簡単ですが、良いところを見つけるには、その人への「関心」と自身の「向上心」が必要になります。
でも、時間がたつにつれて「関心」と「向上心」は薄れ、忘れてしまいます。
そのためには、「初心に帰る」ことが大事で、ブレなくて頼もしい現場監督だと評価されるには、現場でのリーダーシップをとるためにも必要なスキルになります。
初心に帰るための手段を身に付けることで、自分が生きていく方向が明確になります。
その手段の身に付け方、あなたの生き方を正すために必要なものとして、「座右の銘」を決める又は、何度でも読むことができる「愛読書」を見つけるのがおすすめです。
施工管理技術者としてリーダーシップをとるコミュニケーションスキルについては、次の記事でより詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
スキル6:円滑に工事を進める現場監督になるため相手を引き込む会話スキル
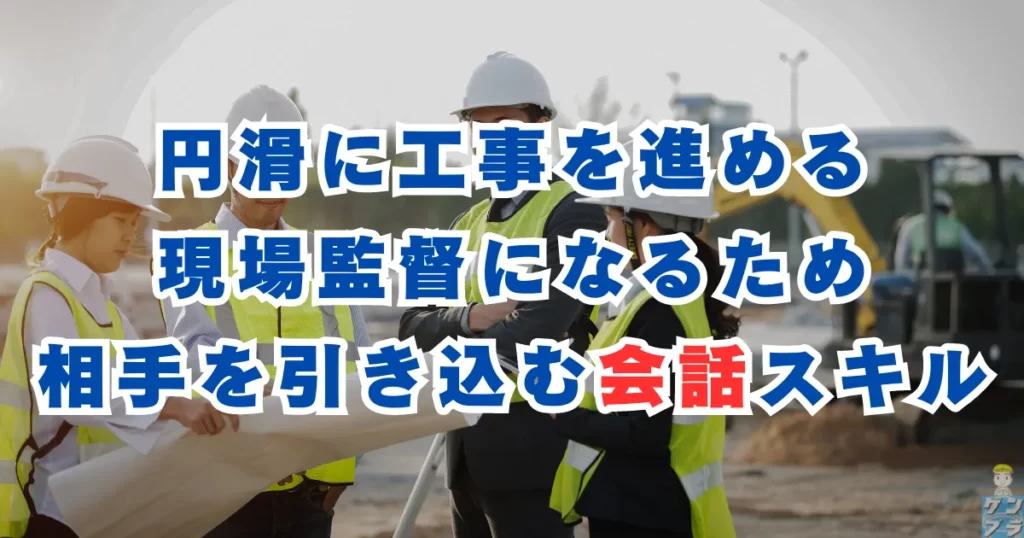
一歩上を目指すために相手を引き込む会話スキルについて。
仕事をする中で、自分のキャラで仕事をするだけでなく、「現場監督を演じる」ことも必要ということを覚えていてください。
普段は物静かで優しい人だとしても、時には現場監督として厳しくしなければ、良い工事現場にはなりません。
相手に興味を持ってもらう会話ができるかどうかは、どちらかというと話すスキルより、話すために行った努力量の方が大切と言われています。
- 話のネタをインプットするための手段をもっているか
- 話のネタをインプットする時間を費やしているか
講演会などで、労働安全コンサルタントの方が建設業に関する安全について、すらすら話しているシーンを見ます。
内容は決められたものではなく、最新のごく数日前に起きた労働災害についても触れながら2時間、3時間と解説していることに対し、単純にすごいなと思いますよね。
文章に書き起こしたらたら何万文字になるのかわからないほどの情報量です。
聞くと、頻繁に講演会に出させてもらっているから、原稿を読まなくても話す内容は覚えているとのことでした。
人は情報をインプットしただけでは記憶に残らず、人に話す・メモに書く・SNSなどネット上に投稿するなど、アウトプットしなければ頭に記憶されにくいものです。
話の内容としては、次のようなものを用意しておくのがおすすめです。
- 自分自身のことを熱く語ることができるスピーチを作る
- 面白可笑しく語ることができる話題をもつ
- 趣味についての話題を持つ
施工管理という技術面のスキル向上も重要ですが、現場監督にとって会話スキルは建設現場を運営するうえで、全てに関わるコアスキルになります。
会話スキルを身に付けるためには、話のネタを仕入れる努力をしないといけません。
ネタを仕入れる方法は、テレビやインターネット以外にも、人を観察するという方法があります。(同じ人を見すぎているとトラブルになりかねないので注意)
スマホを見ている人は、9割の人がムスっと少し怒っているような顔をしていています。
中にはうれしそうな顔をしている人もいますが、ごく稀です。
無意識に不機嫌そうな顔をしているということは、やはりストレスの中で仕事をしているからこそではないでしょうか。
人を観察することが気になる場合、身の回りの出来事に対して感想を独り言でも、頭の中でも構わないのでつぶやくようにしてみてください。
常にアンテナを張って、どんな時でも話のネタ作りを心がけることができれば、会話スキルは向上します。
どんなことでも、始めた時が1番大変です。
まずは1週間頑張ってみる。
1週間後には、最初の頃よりは簡単になっているはずです。
1カ月、3カ月と継続し、1年後には習慣にすらなるほどです。
この習慣化することが大事ですが、9割の人は最初の一番大変な時期に挫折してしまいます。
ですが、より円滑に工事を進めることができる現場監督になるためです。頑張りましょう。
次の記事でより詳しい解説をまとめていますので、こちらも参考にしてみてください。
スキル7:発注者の信頼を得るためのスキル

発注者と良好な関係を築いて信頼を得るということは、現場を運営していく現場監督にとって重要なスキルとなり、工事成績にも影響するスキルです。
信頼を得るための基本となる考え方は、相手の立場を考えることです。
相手の立場を考えるとは、どういうことか。
発注者は何が怖いのかを考えて、怖いものを取り除くように工事を遂行すればよいことになります。
発注者が怖いのは、会計検査官ということになります。
発注者が恐れる会計検査なら、会計検査に引っかからないように受注者が考えて工事を進めていけばいいことになります。
ここが現場監督の腕の見せ所で、信頼を得るテクニックです。
発注者との打合せの際は必ずメモを取りましょう。
これは、打合せ内容を確実に覚える自身があったとしてもです。
メモを取らないのを見たら、この現場監督は自分の言ったことを守って工事を進めてくれるのかと、疑いを持たれます。
技術的なことの前に、少なくとも発注者にそんな心配をさせる現場監督は、信頼を得ることはできません。
それと、打合せの最後に必ず話の内容を1分程度で手短に確認を行うようにします。
さらに、これは発注者の対応によってするか、しないか選ぶべきではありますが、打合せの当日中か翌日までに、打合せ内容をメールしましょう。
電話は相手の時間を強制的に奪うことになるので、この場合は絶対にメールにした方が良いです。
工事打合せ簿として議事録を報告する方法でもいいですが、毎回議事録を作成するのも大変なので、重要な内容に限り議事録を作成するといやり方でいいと思います。
他に、発注者の信頼を得るうえで大切なことは次の通りです
- 期限のあるタスクは、必ずその期限より前に完了させる(レスポンスはできる限り早く)
- 受注から工事開始までの準備期間は、週に1回は発注者と打合せを行い、自分のことを売り込む(打合せのネタを絶えず用意する)
- 初回の現場臨場検査は徹底的に準備を行い、万全の状態で迎える(事前に立会時の資料を再確認し、現場でリハーサルを行う)
- 立会時の資料は、発注者用と自分用とで2部用意し、降雨が予想される場合は耐水紙で資料を印刷しておく
細かいことではありますが、信頼度を上げていくには小さいことの積み上げしかなく、近道はありません。
そして1度の事故や約束を守らないなど、信頼を失うのは簡単です。
僕自身も、あの時はこう対応すればよかったなとか考えることがあります。
発注者にはしっかりと誠意を持って工事に臨みましょう。
発注者の信頼を得るためのスキルについては、こちらの記事でより詳しく解説していますので、良ければ参考にしてください。
スキル8:事故を予防するスキル

現場で働く協力会社の人は新規入場した際に、安全管理のレベルを見ます。
まず、現場で働く人全員が参加する朝礼。
朝礼の場は、現場監督が絶対に事故を起こさないという信念と安全に対する思い入れを伝える重要な場面です。
毎朝必ず、熱意を持って現場の安全への思いを語るようにしてください。
朝礼時の現場監督の一言が事故を防止すると言っても過言ではありません。
しして、現場の状況も言葉に伴っているかも大切です。
まず、現場内の状況。
- 重機の立ち入り禁止措置がとられているか
- 安全に関する看板・標識がいたる所に掲げられて意識向上が図られているか
- 作業通路が明確に設けられているか
- 服装は全員整っているか
- 安全掲示板の内容が充実しているか 等
そして、現場事務所や休憩所
- 清潔に保たれているか
- コロナウイルス対策は万全か
- 新規入場者教育資料の内容が充実しているか(他工事の使いまわしになっていないか)
朝礼の場面
- 暗い雰囲気で朝礼が進む
- 朝礼の言葉に覇気が無い
- ~に注意してくれ等、作業に対する具体的な助言が無い
協力会社の職人はいろんな現場を見ているので、現場に入った第一印象でその現場の安全に対する意識レベルがわかってしまうものです。
なので管理が不十分だと、
「この現場はこれくらいでやっとけば監督さんに文句言われないだろう」
と、安全管理に対してゆるい現場だと感じられてしまい、事故発生のリスクが高まります。
つまり、その現場を担当する現場監督の安全に対する姿勢が問われることになります。
もちろん、朝礼だけで満足してはいけません。
- 現場で作業する人、一人一人に「ご苦労様です」と声をかける
- 危険な作業時は必ず作業を見守る
- 不安全な行動はすぐに指摘・是正する
- 新規入場者教育は入念に行う
どんなに小さな違和感・異変を見逃さないことも大事ですが、これくらいいいかと、見過ごすこともやってはいけないことです。
安全に対して妥協点はありません。
凡事徹底することが、現場の安全の質を高めることになります。
事故発生を防止するためのスキルについて、こちらで詳しく解説していますので、よければ参考にしてください。
まとめ

本記事では、建設業で施工管理を行う現場監督が持つべき、大切なスキルを8つ解説しました。
- 自分の思い通りに現場を管理するスキル
- 現場の問題点を予測するスキル
- 問題解決の順序を決めるスキル
- 現場にトラブルが発生した時のメンタルスキル
- 現場でリーダーシップをとるスキル
- 相手を引き込む会話スキル
- 工事関係者の信頼を得るスキル
- 事故を予防するスキル
施工管理の仕事はやること、覚えなければいけないことが多いですよね。
なので、実際に働いている人で施工管理が楽な職業だという人はいません。
それでも、失敗しながらでも少しずつ経験を積んで、小さな成功体験が『やりがい』に変わっていきます。
 ランメイシ
ランメイシ施工管理の仕事で「壁にぶつかった」とか、「悩みができてしまった」と感じたら、当サイトを是非参考にしてください。
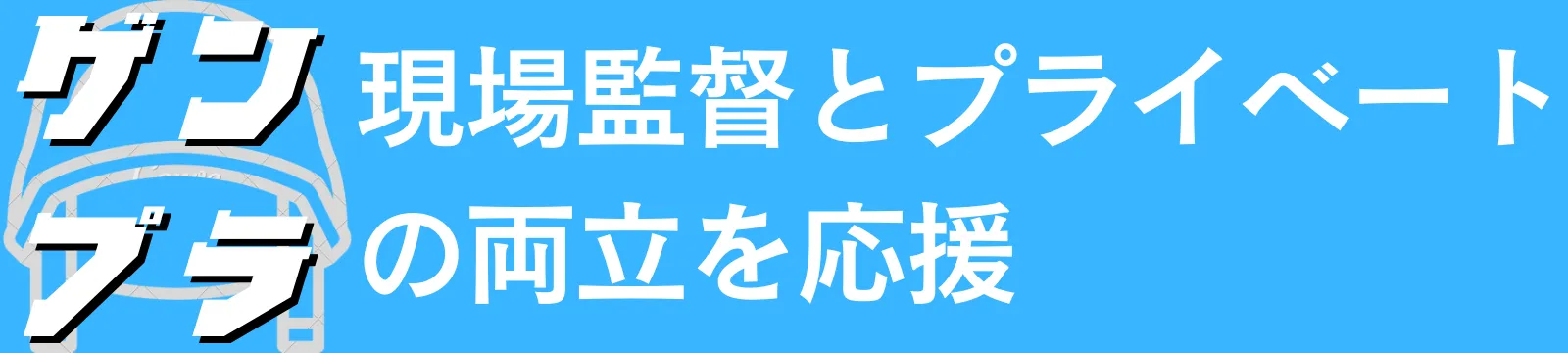

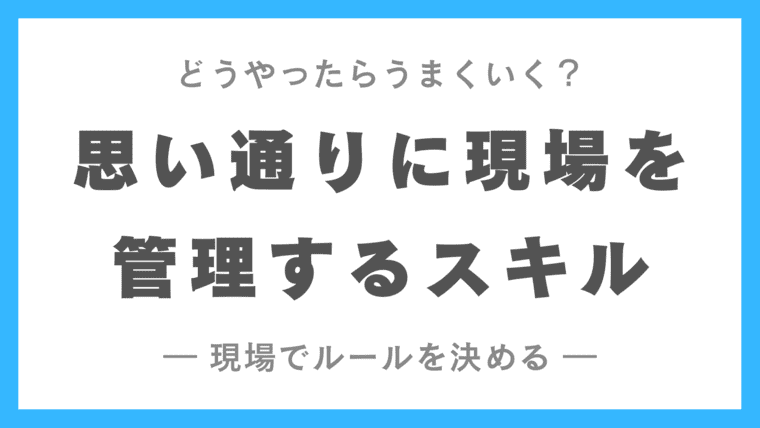
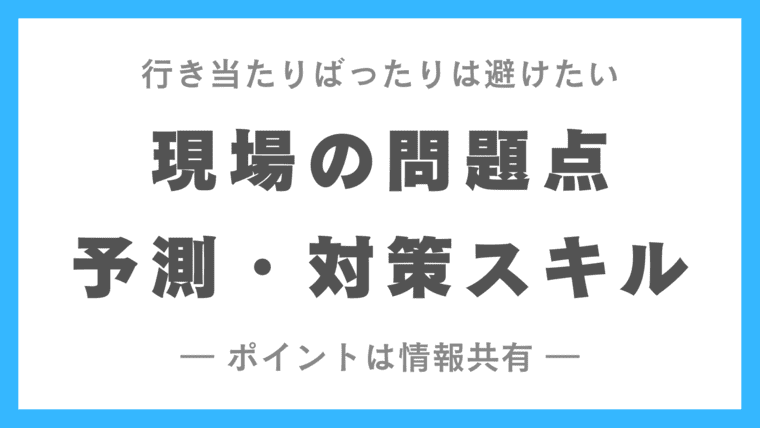
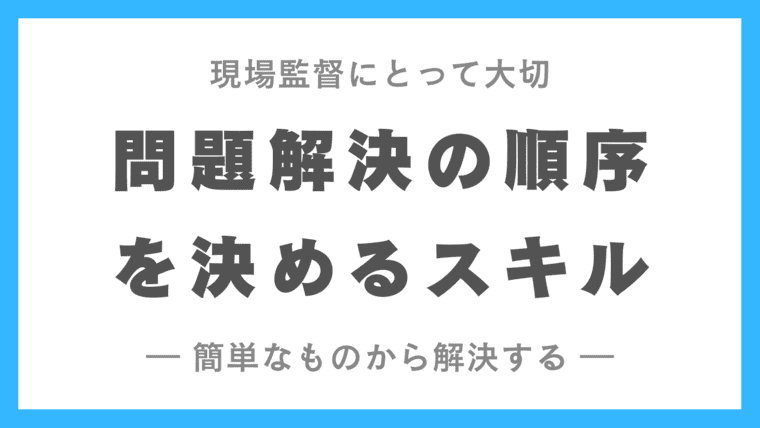
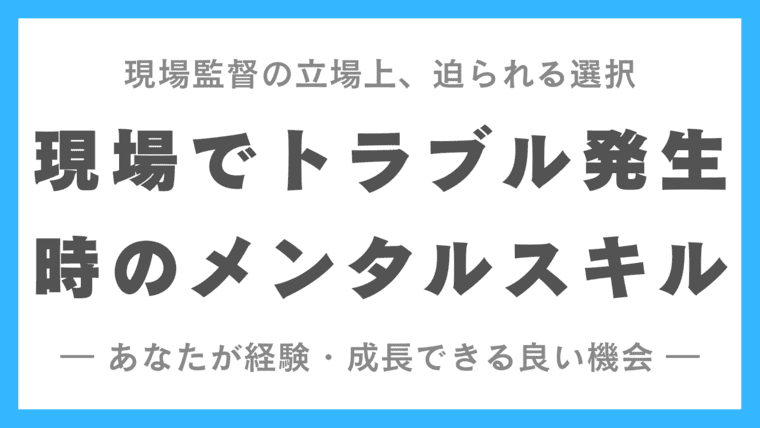
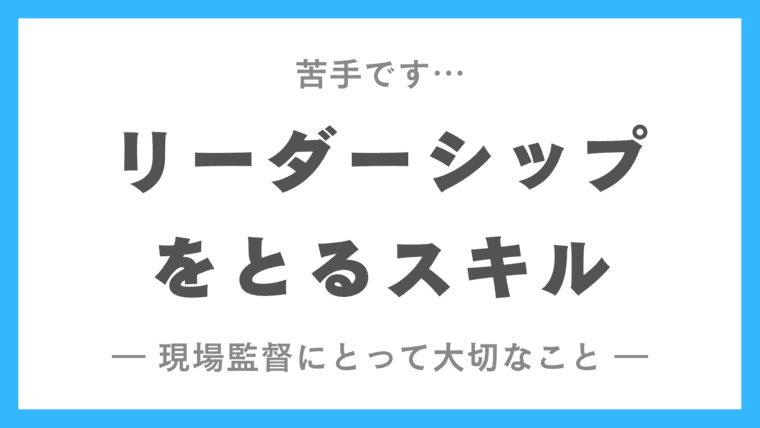
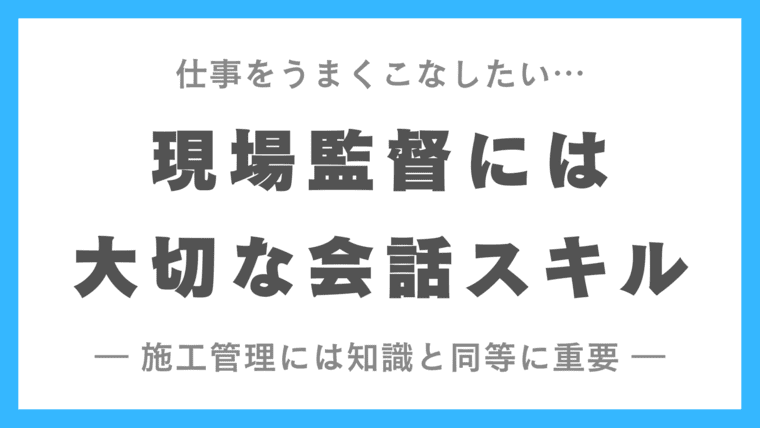
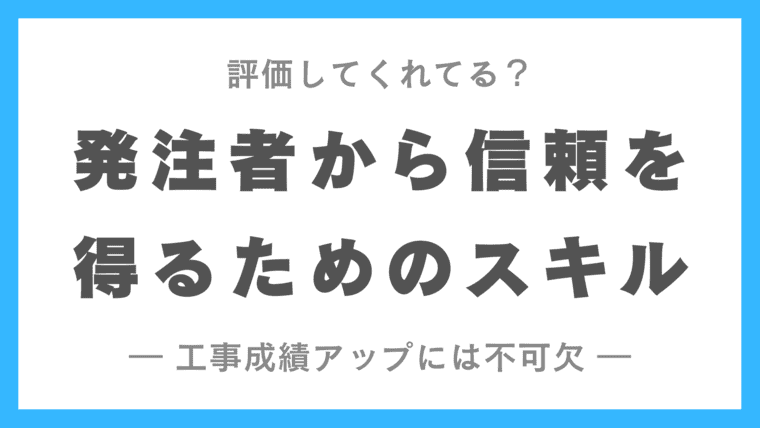
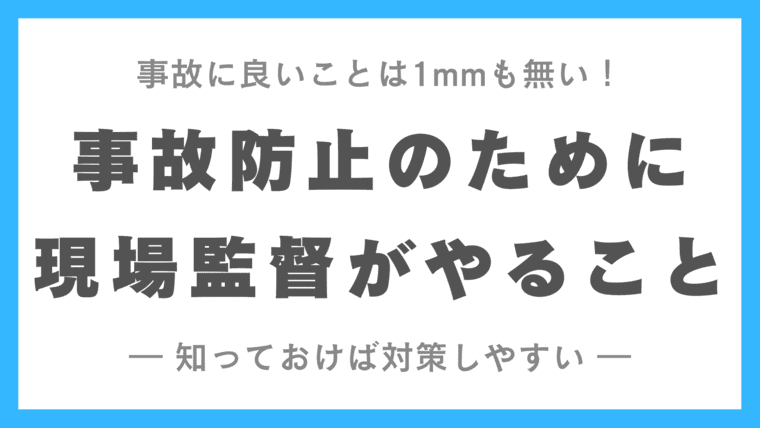
コメント