【梯子から転落】建設工事現場でのヒヤリハット事例から見る安全対策【体験談/イラスト/PDF】
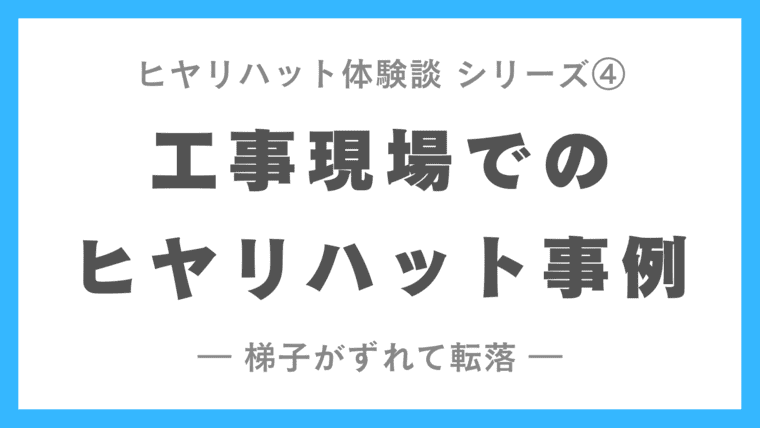
建設現場には『危険』がたくさん潜んでいます。
事故を起こしたくて起こす人はいませんし、事故を起こさないために安全管理を頑張っていますよね。
それでも、工事現場ごとに現場条件が違う建設工事では、『想定外の出来事だった』とか『こんなことが事故になるなんて』という状況が起きるのも事実。
本記事では、僕が現場監督をやっていて実際に体験した、ヒヤッとした経験やハッとした経験。
ヒヤリハット事例を紹介します。
 ランメイシ
ランメイシ本記事のような体験があなた自身に、あなたの現場で起きないよう、ぜひ参考にしてね!
この記事を読むと、以下のことがわかります。
- 工事現場でのヒヤリハット事例と対策
- 梯子でどんな事故の可能性があるか
- 梯子の安全な取り扱い方
- 丁張材を運んでいる途中、段差に躓きそうになった
- 単管パイプの片付け中、周囲の人に当たりそうになった
- ダンプ荷台上で写真を撮ろうとして、転落しそうになった
- 梯子を登っている途中、ズレて転落しそうになった
- 敷鉄板の上を歩行中、滑って転びそうになった
- 墜落・転落災害防止に役立つサイトまとめ
- 玉掛フックが資材に引っかかり、荷崩れした
- バックホウが移動したときに、敷鉄板がズレた
- 積み重ねたバタ角の上に乗ったとき、転倒しそうになった
- 足場上で張り出した単管パイプで顔を打ちそうになった
- ブラケット足場の結束忘れにより、転落しそうになった
- ヒヤリハットを建設現場の労働災害防止への活かし方と問題点の解決法

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ
現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!
保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士
主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事

当サイト『ゲンプラ』の運営者:ランメイシ
現場監督と家庭(プライベート)の両立を応援するために、土木工事の施工管理をやっている現役の現場監督(歴16年)が当サイトを運営。施工管理業務の悩みに全力でサポートします!ご安全に!
保有資格:1級土木施工管理技士、河川点検士
主な工事経験:河川の築堤・護岸工事、道路工事、橋梁下部工事
梯子を登っている途中、ずれて転落しそうになった

仮設ハウスの上に、梯子(はしご)をかけて登っている時のこと。
梯子を登っている途中で梯子がずれて、転落しそうになってしまいました。
梯子から転落しそうになった原因
このヒヤリハット事例で、梯子から転落しそうになった原因は以下の通り。
- 梯子の固定を確認しなかった
- 梯子がずれやすい地面であることを考慮しなかった
- 安全な使い方を知らずに梯子を使っていた
梯子を設置した際にぐらつきが無いか、ちゃんと固定されているかを確認しなかったことが、梯子がずれる原因の1つでした。
梯子から転落の事故を防ぐための対策
梯子から転落の事故を防ぐための対策としては、以下の4つがあげられます。
- 梯子を登り降りする時は、固定されているか確認する
- 梯子を適切な角度(約75度)で設置しているか確認する
- 2人いる場合は、1人が梯子を押さえて固定する
- 2段以上の梯子の場合、ロック金具の固定を確認する
対策としては、梯子を使って昇降するときは固定すること。
梯子を適切な角度(約75度)で設置しているか確認すること。
2人いる場合は、1人がはしごを押さえて固定すること。
2段以上の梯子の場合、ロック金具の固定を確認すること。
などが上げられます。
梯子の安全な使い方
 ランメイシ
ランメイシ梯子の安全な使い方については、下記から詳しく知ることができます。
(出典:ALINCO – はしごの安全な使い方)
現場経験年数の浅い人ほど、はしごから転落する
梯子を使って登り降りするだけ。
単純かつ簡単な動きのため、初めて使うというような経験年数の浅い人でも、梯子の基本的な使い方について詳しく教わる機会がほとんど無いという人も多いです。
『ALINCO–はしごの安全な使い方』にて、梯子の使い方やポイント、間違った使い方について、写真付きで解説されているので参考にしてみてください。
(出典:ALINCO – はしごの安全な使い方)
梯子使用時の主なポイントは以下の通りです。
- 建物との接点は、2段目の踏ざんと3段目の踏ざんの間が理想的
- ロック金具が確実にロックされていることを確認する
- 梯子は補助者が支える
- 梯子から屋根、屋根から梯子に乗り移るときは、補助者が梯子をしっかり支えて、安定させる
数年に1度は耳にする、梯子から転落という事故。
最悪の場合、死亡事故になりかねません。
工事現場での『これくらい大丈夫だろう』が、事故の引き金になることは多いです。
事故・怪我のリスクは、どんなに『小さなこと』でも現場から無くしていくべきですね。
 現場監督
現場監督子がずれる以外にも、踏ざんを踏み外す可能性もあるよね。土木工事だと屋外の使用がメインだから、雨の日はさらに滑りやすくなって危なそう…。
 ランメイシ
ランメイシ屋外で降雨時の梯子を使う時は、普段以上に注意して使わないと、大怪我の可能性があるね。
梯子は基本的な使い方を知っておかないと大怪我の可能性がある
たとえば…
- 梯子の設置角度を75度よりゆるく設置して、梯子がずれる
- 2段以上の梯子のロック金具が固定されていない
- 足元をよく見ずに登り降りして、踏ざんを踏み外す
『ちょっと危ないけれど、こっちの方がは早い』が原因で、失敗や事故につながることは多いです。
落ち着いていれば起きるはずのない事故も、他に考え事をしていたり、忙しくて慌てていたりと、いろんな要因が重なることで事故に繋がってしまうケースも。
現場で同じ状況になったとき、なっているのを見かけたときは注意して、安全な現場環境を維持していきましょう。
【ハインリッヒの法則】ヒヤリハットが起きた=運よく事故にならなかっただけ!
「ハインリッヒの法則」をご存知ですか?
ハインリッヒの法則とは、「1件の重大事故の裏には29件の軽微な事故と300件の怪我に至らない事故がある」というものです。
ハインリッヒの法則は労働災害における怪我の程度を分類し、その比率を表しています。
その数字から「1:29:300の法則」と呼ばれることもあります。
つまり、ヒヤリハットが起きたということは、その時は運よく事故にならなかっただけ。
後で同じヒヤリハットが起きたら、その時は重大事故になるかもしれません。
現場で事故が起きたら、本当に最悪です。
- 「事故速報」を発注者に20分以内など、直ちに提出する
- 原因など、安全管理に問題が無かったか、追及される
- ケガ人が出れば、現場で働く人以外に、ケガ人の家族も悲しむことになる
- 事故報告書を作成し、発注者に提出する
- 事故の内容や発生状況の写真や図を作成
- 事故原因と再発防止対策を現場または社内で検討して作成
- 施工計画書から、事故に関係する施工内容を添付
- 事故に関係する業者の契約書、施工体制台帳の写しを添付
- 事故当日の安全巡視日報の写しを添付
- 事故発生日の危険予知(KY)活動日報の写しを添付
- 事故発生日の作業日報の写しを添付
- 事故に関係する作業手順書の写しを添付
- 災害防止協議会の議事録写しを添付
- 安全教育・訓練の実施内容写しを添付
日頃から安全管理を徹底して、現場も書類も不備が無ければ、事故のリスクは少なくできるでしょう。
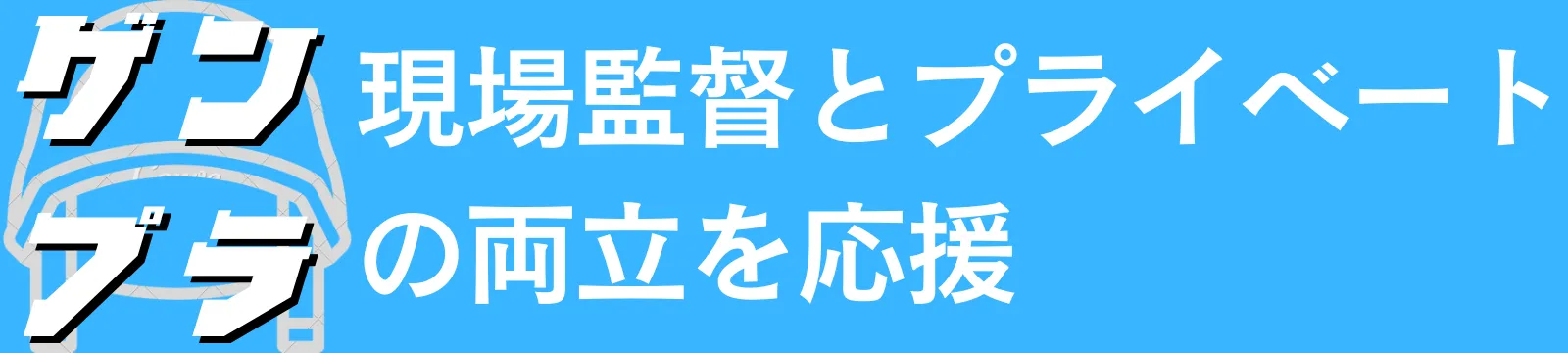

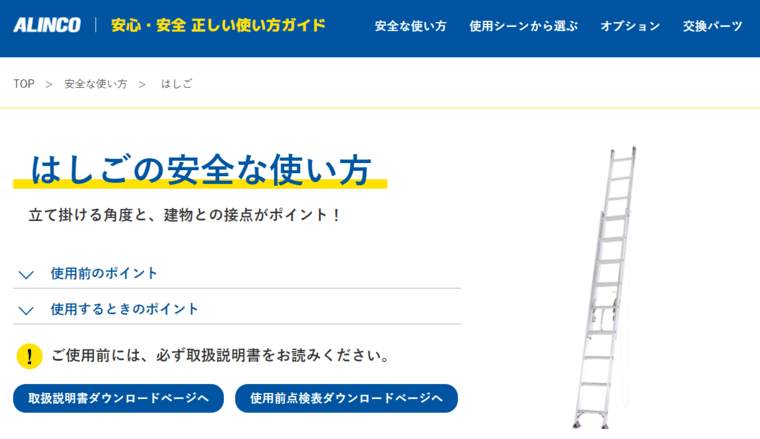

コメント